「同居の家族の中でダニに1人だけ刺されるんだけど何か理由があるの?」
私は同居している家族の中で、ダニに1人だけ刺されることが多いんです。
特に思い当たることがないのに小さな腫れや小範囲の痒みが出たり、布団やソファーでムズムズしたり。
そこで、私だけダニに刺される理由は何だろうって、ちょっと調べてみたところ、実は、ダニに刺されやすい人と刺されにくい人がいることが分かりました。
今回は、ダニに刺されやすい人の特徴や対処法について解説致します。
ダニに一人だけ刺されるのはなぜ?ダニに刺される人には個人差がある

ダニに刺される人には個人差がある
ダニに刺されるかどうかは、個人差によるものが大きいと言われています。
同じような環境で暮らしていても、年齢・性別・体質によって、刺されやすい・刺されにくいということが生じます。
「最近ダニに刺されない?」と家族に聞いても自分にだけ症状が現れていて、ダニではなく他の虫による被害なのか疑ったり、他の病気を考えたりすることもあるかもしれませんが、刺されやすさに個人差があると考えれば、不思議なことではありません。
ダニに一人だけ刺される人の特徴と原因

ダニに一人だけ刺される人の特徴と原因
ダニ 一人だけ刺されるという人には、特徴があります。
1つずつ確認しながら、原因を探っていきましょう。
体温が高い(汗っかきである)

汗っかき
体温が高い場合、ダニに刺されやすくなります。
平均体温が高い人だけでなく、入浴や運動の後で体温が上がっている場合も同様です。
ダニは高温多湿の環境を好みます。
体温で温められた場所に居心地のよさを感じたダニが移動してきて、人を刺すことが考えられます。
また、汗っかきな人や、よく汗や水をふき取らないまま過ごすことが多い人も、同じように多湿を求めてやってきたダニに刺されやすくなるでしょう。
こまめに体温調節したり、汗を拭きとったりすることがポイントです。
アルコールを良く飲む人

アルコールを良く飲む
アルコールを飲むと、ダニが好む二酸化炭素が出やすくなります。
元々人の呼吸には二酸化炭素が含まれますが、お酒を飲むとアルコール分解を早めるために呼吸数が上がり、二酸化炭素の排出が活発になりますので、その分ダニに刺されやすくなってしまいます。
また、体温も上がる傾向にありますから、更にダニが寄ってきやすくなるでしょう。
肌が柔らかい(女性や赤ちゃん)

肌が柔らかい
ダニが人の血を吸うにあたり、皮膚が柔らかい人の方が深くまでキバやツメを刺しやすくなります。
女性や赤ちゃんは特に狙われやすくなるでしょう。
生まれたばかりの乳児がいる家庭はダニによる被害が増えるだけでなく、将来ハウスダストアレルギーを引き起こしたりするリスクが考えられますので、ダニ対策を入念にするのがよさそうです。
また、男性でも体の柔らかい部分から優先して噛まれることが多くなります。
- 二の腕・ふくらはぎ・太ももなどの末端部分
- 脇の下・首筋など、筋肉が少なく鍛えにくい部分
は特に噛まれやすくなります。
ペットがいる家庭

ペットがいる家庭
ペットがいる家庭は、ダニが発生しやすくなります。
ダニは卵から生まれるとすぐに人や動物にくっつき血を吸いたがる習性があり、獲物を待つために草の先端や花の花弁などに乗り移ります。
散歩中のペットが草花に近づくことで、自宅にダニを持ち込んでしまうケースも少なくありません。
また、人よりもペットの方が入浴する頻度が低いこと、体毛があり体温が保たれやすいことなども、ダニの繁殖を助ける一因となっています。
草むらなど野外によく行く

草むらなど野外によく行く
キャンプや山登りなどが趣味で野外によく行く場合、ダニを持って帰ってくる可能性が高くなります。
芝生のある公園や落ち葉の多い道なども同様にダニが多い場所であり、気づかないうちに服の裾や袖についてきてしまうこともあるでしょう。
マダニは3~4月頃から増加しはじめ、10~11月頃が本格的な活動期となります。中には、冬季に活動する種類も。最近では、 山・公園・河川敷・草地・庭など身近な場所での存在も問題視されています。
引用:ダニの生態・種類|アース製薬
身体についた全てを落とすことは難しく、「一人だけ刺される…」と感じる要因になります。
家の中ではあまり見ない種類を持ち込んでしまうこともあるため、外出から帰った時は速やかに着替えるかお風呂に入り、拡散しないようにすることが大切です。
ダニに刺された時の対処法

ダニに刺された時の対処法
ダニに刺されると、痒みや痛み、ムズムズした感覚に悩まれます。
まずは不快感を取るための対処法を調べ、実践してみましょう。
市販のかゆみ止めを塗る

市販のかゆみ止めを塗る
市販のかゆみ止めはドラッグストアや薬局で簡単に入手できます。
ステロイド外用剤
湿疹や皮膚炎に使用するのが一般的なかゆみ止めですが、他にもかぶれ・虫刺され・しもやけ・あせもなど、さまざまな皮膚トラブルに対し使用できるのが特徴です。
炎症が起きる根本の部分に効くため即効性が高く、新たなかゆみを呼び起こしにくくなります。
非ステロイド抗炎症外用剤
ステロイド外用剤と同じ用にかゆみや皮膚炎に効果がある薬です。
広範囲かつ長期的な使用もしやすく、使い勝手がいいのでかゆみの程度が軽い場合でも気軽に使えます。
特に、目元・口元など粘膜に近い部分に用いる時や、足全体など広く塗りたい場合には、非ステロイド抗炎症外用剤を使うのがよいでしょう。
内服薬
飲み薬で痒みや湿疹を抑えられるものもありますが、ダニによる被害の場合、被害が非常に重い時に限りごく一時的に使うのが一般的です。
かゆみを起こすヒスタミンという体内物質を抑制する効果があり、塗り薬と併せて使うのもおすすめです。
掻きそうになったら冷やす
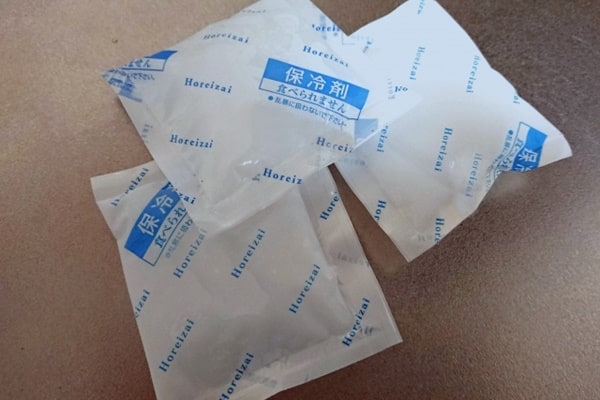
掻きそうになったら冷やす
かゆみが我慢できない場合でも、かきむしってしまうのはNGです。
肌や爪を傷つけてしまうだけでなく、傷から細菌が入って二次感染が起きたり、皮膚炎に発展したり、デメリットが多いものです。
かき壊してしまうレベルにまで至ると、外傷として処置する必要まで出てきますので、かきむしりが癖にならないよう注意しましょう。
どうしてもかゆみが引かず我慢できない時は、刺された場所を冷やします。
皮膚表面が急激に冷やすことで血管を収縮させ、かゆみを伝える神経を鈍らせるのが目的です。
特に刺されてすぐ行うと高い効果が期待できますので、気づいた時には早めの対処が肝心です。
保冷剤で冷やす
自宅に保冷剤がある場合、小さなタオルや布巾で包んで当て続けます。
長時間同じ場所に当て続けてしまうと肌がチクチクしたり凍傷になったりする場合がありますので、注意が必要です。
定期的に位置やタオルを変えながら行いましょう。
冷水で冷やす
手足であれば、冷水を直接当てることで冷やすのもおすすめです。
桶に溜めた水ではなく、なるべく流水で洗うようにすることで、皮膚表面のダニや汚れを除去しながら冷やせます。
氷水を使ったり、あまり長い時間続けたりすると体全体の温度が極端に下がってしまいますので、2~4分程度で十分です。
濡れタオルを当てる
タオルやハンカチを濡らし、しばらく巻き付けておくだけでも効果が得られます。
固く絞りすぎず、少し水分が感じられる程度におさえておけば、より早く冷やせるでしょう。
冷やす効果だけではなく発汗を抑える効果もあるため、草むらに入る時など事前に行っておくのもおすすめです。
皮膚科を受診する
かゆみがなかなか収まらない時や長期的な被害に悩まされている場合、皮膚科を受診して専門家のサポートを受けるのもよいでしょう。
ダニ刺されによる痒みは、血を吸われる際に体内に混入してしまう唾液腺物質に対するアレルギー反応ですから、アレルギー症状を抑える薬を処方してもらえます。
特に、マダニに刺された場合は無理に自分で処置せず、速やかに皮膚科に行くことが大切です。
痛みや痒みなどの症状が出ないこともありますが、マダニが持っている病原菌に感染してしまう場合もあり、日本紅斑熱、ツツガムシ病、熱性血小板減少症候群(SFTS)等が有名です。
自然に取れた場合でも、紅斑や発熱がないか、1~2週間程度は慎重に様子を見ておきましょう。
マダニに刺されると、日本紅斑熱やライム病などの感染症や、問題となっている「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」を発症する場合があります。日本全国でこの「SFTSウィルス」を保有したマダニが確認されており、国内で広く分布していると考えられています。「SFTSウイルス」を持ったマダニに刺された場合、潜伏期間は6日~2週間程度。発症した場合の主な症状は、38度以上の発熱、嘔吐、下痢、食欲低下です。致死率は6~30%と報告されていますが、治療法として有効な薬剤やワクチンは現状ありません。
ダニに刺されないための予防と対策法

ダニに刺されないための予防と対策法
ダニに刺された後の対処法も重要ですが、なるべくなら刺されずに済みたいものです。
ここでは、ダニに刺されないための予防・対策法について紹介致します。
家をこまめに換気する

家の換気
家をこまめに換気して、新鮮な空気を取り込むことが大切です。
ダニは高温・多湿の場所を好みますから、定期的に空気を入れ替えて室温を下げ、ダニが繁殖しづらい家を作りましょう。
家が湿気っぽくならないよう、雨の日を避け、カラッと晴れた天気のいい日に行うのがポイントです。
掃除・洗濯をする

家の掃除
家全体をこまめに掃除・洗濯し、ダニが繁殖する環境を与えないようにします。
ダニは、人のフケ・皮膚・垢・髪の毛・ホコリなどを好みますから、これらが溜まってしまいそうな箇所はよく掃除しておきましょう。
ソファーやクッション

ソファー
ソファーやクッションの掃除はマメにカバーを取り外し、洗濯します。
掃除機をかけてゴミを取り除いたり、外の乾燥した空気を取り入れて湿気が増えすぎないように注意したりするのもおすすめです。
掃除機のノズルが入り込みにくいソファーの内側にはダニ取り用シートを入れるなど、手の届かないところまで対策しておけば更に安心できそうです。
布団

布団乾燥機
敷布団・掛布団共にシーツを取り外し、定期的に洗濯します。
布団クリーナーでゴミを取ったり、天気のいい日に干したりするのもよいでしょう。
ベッドの場合、マットレスを外して壁にたてかけ、湿気がこもりすぎないよう対策することも重要です。
布団乾燥機を使って除湿し、ダニが繁殖しづらいようにするのもポイントです。
絨毯やマット

絨毯にいるダニ
外に干す・ダニ退治用グッズを使う・クリーニングに出すなど、さまざまな方法が考えられます。
ダイニングテーブル下のマットは食べカスが溜まりやすく、玄関マットは足裏の皮脂や汗が吸着しやすいため、定期的に掃除することが大切です。
カーテン

カーテン
カーテンにも意外とダニが潜んでいます。
窓を開けて風に揺れることで家中に飛散することもありますので、マメな手入れをするのがよいでしょう。
丸洗いできる素材のカーテンであれば洗濯機で洗い、洗えない素材であれば天日干しやクリーニングをするのはおすすめです。
ダニは60度程度の熱を与えることで死滅すると言われているため、プリーツの形やシワに注意しながらアイロンを当てるのも効果的です。
畳

畳の部屋
畳にも意外とダニが発生します。
掃き掃除でゴミを取るのはもちろん、水が垂れないよう固く絞った雑巾で拭き掃除をしましょう。
畳に傷や毛羽立ちが生じないよう目に沿って丁寧に拭き、畳を取り外して立てながらしっかり乾燥させます。
乾燥させきらないまま使ってしまうとかえって湿度が増し、ダニが増えたりカビが発生したりする恐れもありますので、注意して行いましょう。
ダニ取りシートを使う
市販されているダニ取りシートを使い、ダニを駆除する方法です。
布団の裏やソファーの隙間に設置するだけで使えるためほとんど手間がかからず、交換も数ヶ月に1回で済むため、毎日こまめにダニ対策をする必要もなくなります。
家に出やすいヒョウダニ・コナダニ・ツメダニ・イエダニに特化して開発されていることが多いのが特徴です。
ダニが好む香りで誘い込み、一度に処分してくれるので効率もよいでしょう。
ダニ用スプレーを撒くのもおすすめですが、小さな子どもやペットがいて空気中に薬剤が残ることを心配するご家庭なのであれば、ダニ取りシートの活用がおすすめです。
ダニ駆除業者に依頼する

ダニ駆除業者に依頼
ダニ駆除に特化した業者を呼び、家中まとめて掃除してもらう方法もあります。
しっかり掃除してもなかなか効果が得られない場合や、しばらく使っていない古い家屋をクリーニングしたい場合に便利です。
生きているダニはもちろん、ダニの糞や死骸も取り除き、ダニがまた発生しないよう予防までしてくれる業者もあります。
口コミや価格を比べながら業者を選びましょう。
まとめ
ダニが発生すると痒みや痛みに襲われるだけでなく、肌が荒れたりくしゃみが止まらなくなったり、ハウスダストアレルギーに発展することも考えられます。
最初は一人だけ刺されるという場合でも、どんどん繁殖することで家族全員に被害が及んでしまうかもしれません。
ダニを退治して家を清潔に保ち、快適に暮らせる我が家をキープしていきましょう!


